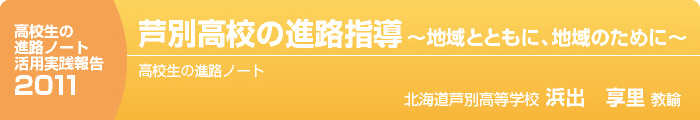

北海道芦別高等学校は、2010年11月に創立70周年式典を挙行した。現在は市内唯一の高校となったが、芦別市内の閑静な住宅地の一画にあり、校舎の近くには空知川が流れるという恵まれた自然環境の中、生徒は落ち着いた学校生活を送っている。北海道の中央部に位置し、かつては「炭鉱のまち」として人口も最大7万5千人余りに達していた芦別市の主な産業は、炭鉱から米などの農林業へと移り変わってきた。
芦別高等学校の進路目標である「自らの力で進路を切り拓き、社会で生き抜いていくとともに社会に貢献する人間を育てる」のもと、先生方の温かい眼差しで行われている進路指導は、生まれ育った地域に貢献できる社会人として、着実に生徒を成長させている。
◆本校のキャリア教育
 本校の進路決定状況は、民間企業への就職・公務員・専門学校、短大、大学への進学等と幅広いです。素直に育ってきた生徒たちには、社会を生き抜く力を身につけ、その力を持って社会、生まれ育った地域に貢献してもらいたい、という想いがあります。
本校の進路決定状況は、民間企業への就職・公務員・専門学校、短大、大学への進学等と幅広いです。素直に育ってきた生徒たちには、社会を生き抜く力を身につけ、その力を持って社会、生まれ育った地域に貢献してもらいたい、という想いがあります。
本年度(22年度)からは、ただ漫然と対処療法的に、就職指導や進路指導を繰り返すのではなく、3年間を見据えて進路指導を行うべきではないか、という考えのもと、「進路シラバス」を作成しました。その際、進路指導部として、進路目標と目標実現のための柱を明示し、全教員が同じ理念を持って生徒と向き合うことになりました。
芦別高校の進路シラバスの「ねらいと目標」 <クリックで拡大>
<クリックで拡大>
これにより、進路指導部では、学校全体で体系的に見通しを持って生徒を育て社会に送り出すための働きかけが、やがて、学習指導や生徒指導の体系化につながり、それが学校全体を変化させ、地域からも愛される学校になるはずである、という想いを強く持ちました。
◆総合的な学習の時間(CS)の取り組み
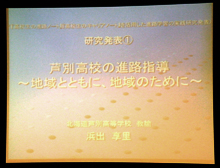 「進路シラバス」に先駆けて、平成20年より、総合的な学習の時間をCS(Course Study)の時間と称し、進路指導・キャリア教育として、「卒業生講話」、「職業人講話」、「職業説明会」、「職場体験実習(インターンシップ)」を実践していました。CSにおいては、できる限り生徒自らが何かを考える時間とさせるため、生徒にとって一番身近な地域住民の力を借りて、教員はそのための支援役に徹する、という一貫した考えで運営しています。平成21年には、地域に愛され貢献できる芦別高校目指し、情報ビジネス科にのみ行っていた職場体験実習を2学年全員実施に切り替えました。進路指導部では教員が約1カ月かけて市役所、商工会議所、商店街、など市内の事業所へ実施の意義や概念、目標を説明しました。中には思わしくない反応もあり、さすがに人口2万に満たない小さな街で、130人の高校生を一斉に職場体験を実施するという企画は無理があるのか、とあきらめかけたこともありました。しかし「これからの芦別に必要である」「よく来てくれた」という事業者の方からの声もあり、このような励ましを胸に“必ず地域に貢献できるはずである”という想いで、5月には無事、第1回目の職場体験実習が実施することができました。
「進路シラバス」に先駆けて、平成20年より、総合的な学習の時間をCS(Course Study)の時間と称し、進路指導・キャリア教育として、「卒業生講話」、「職業人講話」、「職業説明会」、「職場体験実習(インターンシップ)」を実践していました。CSにおいては、できる限り生徒自らが何かを考える時間とさせるため、生徒にとって一番身近な地域住民の力を借りて、教員はそのための支援役に徹する、という一貫した考えで運営しています。平成21年には、地域に愛され貢献できる芦別高校目指し、情報ビジネス科にのみ行っていた職場体験実習を2学年全員実施に切り替えました。進路指導部では教員が約1カ月かけて市役所、商工会議所、商店街、など市内の事業所へ実施の意義や概念、目標を説明しました。中には思わしくない反応もあり、さすがに人口2万に満たない小さな街で、130人の高校生を一斉に職場体験を実施するという企画は無理があるのか、とあきらめかけたこともありました。しかし「これからの芦別に必要である」「よく来てくれた」という事業者の方からの声もあり、このような励ましを胸に“必ず地域に貢献できるはずである”という想いで、5月には無事、第1回目の職場体験実習が実施することができました。
◆インターンシップにおける『進路ノート』の活用
インターンシップ2回目となった平成22年は、事前・事後指導、実習日当日に「進路ノート」を活用し、理解を深めさせることにしました。
(1)事前指導・準備→<準備シート>の活用
事前準備として、電話応対・マナーの指導を行った後、生徒自らが実習先に電話を入れ、挨拶、実習時間や用意するものを確認しました。さらに、当日は『進路ノート』に基づいた職業インタビューを行うことを実習先へお願いしました。
『進路ノート』にある「この体験学習をとおして知りたいこと」「この体験学習で身につけたいこと」には、教員たちが想像を超えた具体的な記述があり、日頃の様子だけではわからない生徒の気持ちを知ることができました。特に「仕事の大変さや厳しさを知りたい」、「コミュニケーションの力を身につけたい」、「挨拶とか礼儀をしっかりしたい」という彼(彼女)らの言葉は、世の中で広く言われていること、あるいは我々教員が日頃からよく話していることの受け売りなのかな、とも受け取れます。しかし、そうであったとしても、そのことが社会に出るにあたって、ひょっとしたら重要なのかもしれない、と生徒たちが感じていることは事実であり、この実習で気をつけたいこととして書いてくれていることは、嬉しいことであり、大変頼もしく思われることでした。
(2)インターンシップ当日→<体験シート><職業インタビュー(調査シート)>
 <クリックで拡大>
「職業インタビュー」は、実習の合間を縫って調査を実施しました。「その方のイメージ」には大変ユニークな記述やイラストが数多くあり、日頃言葉で表現することの苦手な生徒でも、実に生き生きと表現していました。
<クリックで拡大>
「職業インタビュー」は、実習の合間を縫って調査を実施しました。「その方のイメージ」には大変ユニークな記述やイラストが数多くあり、日頃言葉で表現することの苦手な生徒でも、実に生き生きと表現していました。
「職業観・勤労観インタビュー」の解答は、実体験に基づいたプロの気迫と誇りを感じさせるものでありました。生徒たちにとっては、私たち教員が伝えるどんな言葉よりも心に響く言葉であったと想像できます。
この項目を読むことは、私たち教員にとっても大変勉強になり、生徒たちの動きが生き生きと読み取れます。体験前にある程度“働く”というイメージができていた生徒も「誇らしそうな顔」や「楽しそうな顔」というのは、想像を超えたはずです。この3日間は、「高校生でも想像可能な職業観」を根底から覆すような貴重な時間であり、財産になったと思われます。働くとは何か、仕事って何なの、会社ってどんなところなのという、初めての体験は、社会人準備期間の高校生にとっては、非常に衝撃的な体験であったことが、これらのシートから感じとることができました。
(3)事後指導・報告会・受入れ事業所による評価→<評価シート>
 課題となっていた事後指導は、インタビュー・座談会形式で体験を報告する形を行いました。さらに、受け入れ事業所にも参加していただき、講評と講話のお願いをしました。報告を聞く生徒は「進路ノート」を持ち、代表生徒の報告と自分の体験を比べながら話を聞きました。
課題となっていた事後指導は、インタビュー・座談会形式で体験を報告する形を行いました。さらに、受け入れ事業所にも参加していただき、講評と講話のお願いをしました。報告を聞く生徒は「進路ノート」を持ち、代表生徒の報告と自分の体験を比べながら話を聞きました。<評価シート>からは生徒たちの様々な思いが読み取れ、生徒に大きな変化がみられます。「ありがとう」「ごくろうさま」「また来てね」というお客様からの言葉は、働くものの最大の喜びであることを実感したようです。「上手だね」という褒め言葉は、お世辞が半分を占めていると考えても、働こう、頑張ろうという意欲を掻き立ててくれるものだし、将来、社会に巣立ったときに、「人の役に立つことが社会人のあるべき姿のひとつである」という考え方を創り出してくれるのではないかと期待します。
◆今後の課題
他の都道府県と同じく、北海道は経済的にも落ち込みが激しく、中でも本校の所在地である空知地方は、石炭産業衰退後の展望が開けないまま、何とも言えない閉塞感が広がっています。「地元に残りたくても、地元に仕事がない」という如何ともしがたい事実が生徒、保護者、そして我々職員に重くのしかかっています。しかし、「どうせ無理」というセリフだけは排除したいのです。地域の方々と、しっかりと力をあわせて、じっくりと子どもたちを一人前の大人に育てたい、この想いは忘れたくありません。
また、今回の実習で活用し、生徒が記述した「進路ノート」の一語一語は、学校が、街が、そして何よりも生徒たちが、光り輝くための貴重な手掛かりであります。これで終わり、ではなく、これをどうするのか、が夢を持ち続けるための我々の課題でありましょう。
