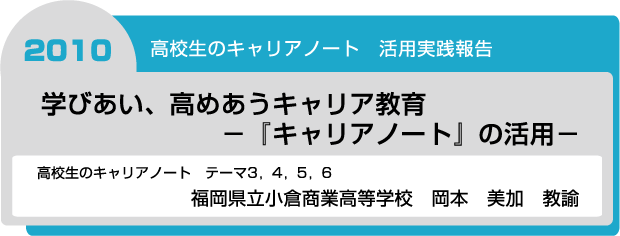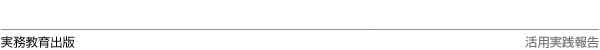●PROFILE
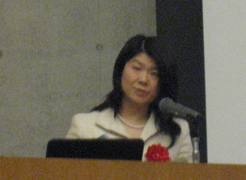 |
本校は、今年で創立93年目を迎えた歴史と伝統を誇るビジネス(商業)教育に関する専門高校です。生徒は非常に素直で、その気にさせればとても力を発揮します。保護者には卒業生が多く、学校への期待が大きいことの現われでもあると感じています。
「清く、明るく、健やかに」を校風に知・徳・体の調和のとれた生徒の育成を目指しています。また、フロンティア・スピリットを建学の精神に、何事にも進んで実践する人材を育成し、徹底した学習指導と充実した部活動、特色ある学校行事により、資格取得や特技の習得を推進し、なかでも、文化祭「倉商祭」の倉商マーケットでは、「株式会社倉商」を立ち上げ、生徒自ら仕入れ、販売、決算までを行っています。このように、進学や就職の夢を叶える学校づくりを進めています。 |
【福岡県立小倉商業高等学校 岡本美加教諭
】 |
*進路状況:大学・短大進学40% 専門学校進学25% 公務員0.4% 就職 35%
(平成21年度卒業者)
●本校の「学びあい、高めあう」キャリア教育について
福岡県の商業高校の拠点校でもある本校のキャリア教育は、目前の進学率や就職内定率に捕らわれず、生徒一人ひとりの進路を長期的な視野に立って指導しています。
学校でのキャリア教育ということですから、学級や学年の中で、お互いを高めあう視点を大事に考えています。私はよく、小論文の指導で行き詰まった生徒には、「縦軸と横軸で考えるように」とアドバイスしています。縦軸は時代の流れを考える、横軸は世の中を広くみるということです。たとえば環境問題というテーマを考えるときに、「現代でリサイクルはこうだが、江戸時代はどうだったか」が縦軸で、「日本ではどうか、外国ではどうか」が横軸です。このような見方で、進路、キャリア教育に視点を広げてとらえてみると、「学びあい、高めあう」ことを考えるときに、縦軸は「生徒同士、保護者、地域、卒業生」、横軸は「他校の生徒と学びあう、切磋琢磨」となり、幅広く考えを深めていくことができます。
<キャリアガイダンス部の取り組みとねらい>
1.課外授業
・それぞれの進路希望に応じた学習指導
2.土曜セミナー
・1、2年生 「キャリア教育の推進」
・3年生 それぞれの進路実現のための進路希望別に実施
3.進学合宿
・受験に耐えうる基礎学力の育成と進学に対する心構えや意欲を培うために行っている合宿
4.出前講義
・高大連携の一環として高校と大学をつなぎ、大学を身近に感じさせる
5.大学見学会
・高校卒業後の進路を見据えた大学見学会
・働きながら大学へ通う学生の声を紹介すると就職から進学へ変更する生徒もでてくる
6.面接指導(就職希望者対象)
・継続的な面接指導を実施
・目先の就職先を決めることにとどまらず、悔いのない人生を送るためにも納得して働くことができるような就業教育を行う
<総合的な学習の時間「キャリアプラン」における『キャリアノート』の活用事例>
1.職業研究 1年生 総合的な学習の時間
◆テーマ3. 職業 いろいろ発見 (6月)
アルバイト、派遣社員、正社員など働き方の違いを学習しましたが、ちょうどこの時期に「派遣切り」が問題視されていましたので、生徒は非常に良い反応を示していました。
|
|
|
キャリアノートテーマ3 ↑クリックで拡大します |
◆テーマ4. インタビュー 職業人 (7月)
身近な職業人にインタビューを実施しました。
この後、まとめ、クラス発表会を経て、最終的には地域の方たちも招いた学習成果発表会を行いました。生徒たちは仕事のやりがいを感じ、このような発表を通して、プレゼンテーション能力を高め、互いに学びあうことができました。
|
|
|
キャリアノートテーマ4 ↑クリックで拡大します |
2.学問研究
◆テーマ6. 進学いろいろ発見(5月)
上級学校の種類や学習分野について知ることを目的に学習しました。また、6月には教育実習生に、現役大学生からの後輩へのアドバイスをいただき、生徒は先輩である教育実習に「どのような高校生活を送っていたのか」、「その大学を選んだ理由」などをインタビューしてまとめました。
|
|
|
|
|
|
| 「将来を考える」のプリント
↑クリックで拡大します |
キャリアノートテーマ5 ↑クリックで拡大します |
|
◆テーマ5.高校3年間の設計図 (3月)
生き方を考える契機としました。 |
|
|
キャリアノートテーマ5 ↑クリックで拡大します |
<『キャリアノート』活用後の発展的指導>
1.ふれあい合宿
2.進学合宿
3.インターンシップ
●成果と今後の抱負
このように、キャリアノートを活用しながら1年生の早い段階で進路について考える機会を多く設定した結果、1学年終了の時点で、前年は40名いた進路未定者が0名になりました。早い時期からキャリアを考えさせる取り組みが功を奏したといえます。希望実現の第一歩は、こういった早めの進路決定だと思っていますので、これからも継続していこうと考えています。
これまで本校ではさまざま取り組みを行ってきていますが、日々の積み重ねが実は一番大事なのではないかと思っています。育てたように子どもは育つといいます。私たち教員が何を考え、何を目指しているのか、それを明確に示して話して聞かせ、地道に体現していくことが、生徒の心に着実に刻み込まれていくのではないかと考えています。
これからも、生徒、保護者、そして地域の期待を超えるような学校を目指していきたいと思います。
|